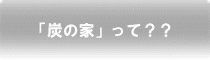
ゴルフ場の芝生は美しさを保つために農薬を使われています。最近では炭を土壌改良材として使うことによって芝の生育をよくし、農薬を減らす方法が注目されています。また、ゴルフ場から流れる水が汚染さてているため、河川や農業への影響が心配されますが、地価の排水溝や調整池流入口に炭を使用することによって解決することが期待されています。
平安時代、貴族の女性たちは十二単を身に着け、あまり動き回らなかったとはいえ現在のようなお風呂の習慣もなく少しは匂いが気になったのではないでしょうか。香を焚きしめたのも体臭をごまかすためといわれています。炭もにおい消しとして使われていたようです。大量の炭が置かれていたという記述もあります。

ホルムアルデヒドなどの有害物質によるシックハウス症候群に炭のパワーが効きます。隅には有害物質を吸着・分解する作用があり有害物質をノックアウトしてくれます。クレーンな空気の中、健やかに暮らすために炭のパワーに頼ってはいかがでしょうか。
・そもそも「炭」って??
・「炭」のエピソード
∟お墓との関係??
∟茶の湯との関係??
∟花粉症との関係??
∟法隆寺との関係??
∟腹痛との関係??
∟紫式部との関係??
・「炭」の現代活用事例
∟ホタルが!!
∟野菜が!!
∟豚のあれが!!
∟ゴルフ場が!!
・炭の七不思議
∟空気がきれい
∟家を泣かせない
∟香り立つくらし
∟じっくりしっかり
∟永いおつきあい
∟こころの栄養
∟時代を活きる
日本では縄文時代の遺跡から炭が発見されていますが、本格的に炭焼きの技術は空海がもたらしたといわれています。以来、さまざまな形で活用されてきました。1300年前に建てられた法隆寺では建物の下には大量の炭が埋められています。伊勢神宮や京都の神社仏閣でも炭を地中に埋めています。調湿作用や防腐作用で建物を守る知恵だったのです。また、場所も電位差のある場所に建っており、炭が発するマイナスイオンによって神社仏閣に神聖な雰囲気をつくっています。
戦国時代、武将たちはこぞって茶の湯をたしみました。その理由は定かではありませんが、ひとつ思い当たることがあります。茶の湯ではまず炭をおこして湯を沸かしてますが、炭のマイナスイオンによって、ストレスの多い武将たちは癒されたのではないでしょうか。茶道用炭で有名な「池田炭」はおこすといい匂いがし千利休のお気に入りだったようです。
炭は何千年も人とともにあります。
焚き火や料理にと使われてきました。
その構造的特性は人工的には決してつくることのできないものです。
木と同じように細いパイプの束が縦横にはりめぐらせていてミクロの穴が無数にあり、しかもそれが外に通じた多孔構造になっています。
そのため表面積が非常に大きく、1gの木炭が300m2もあるほどです。
たとえばピーナッツ1粒で200畳くらいの表面積!!
この多孔構造が炭のパワーの源です。
さらに豊富なミネラル分を含みアルカリ性でマイナスイオンを発する・・・・
こうした特性からさまざまな利用法があることも昔から知られ、燃料以外にも活用されてきました。
パソコンや携帯電話、家電製品など電磁波を発するものが多く、まだはっきりわかっていないとはいえ、人体への影響が心配されています。その電磁波も炭はカットするという実験結果があります。もしかすると炭は未来社会の救世主かもしれません。
炭素のかたまりである炭にはマイナス電子がたくさん含まれていて、まわりにマイナスイオンをまき散らします。そのため森や滝、波打ちぎわと同じようなヒーリング効果が炭にはあるといわれています。ストレス解消にも炭は強い味方のようです。
2000年前の中国のお墓のエピソードから炭には防腐効果があるのではないかと考えています。雑菌を寄せ付けない?または活性化させない?法隆寺の場合はシロアリ退治に炭が効果的だったのかもしれません。暮らしのすみずみに炭の防腐効果を活かしたいものです。
焼鳥や焼き肉、魚などを炭火で焼くとおいしくなるのは、遠赤外線がグルタミン酸を増加させれため。遠赤外線は私たちの体を芯からあたためてくれる効果もよく知られています。炭をお風呂に入れたり炭を練りこんだ衣類を身につけて冷え性を解消します。
冷蔵庫の脱臭剤、空気清浄機などに活性炭が使われているように炭の消臭効果は群を抜いています。暮らしの中にはタバコやゴミ、ペットなどさまざまな匂いがありますが、炭を使えば匂いも解消。香りが強すぎる脱臭剤を使う必要もなく、爽やかな暮らしを実現できます。
炭は多孔構造になっています。その孔が湿気が多くなると水分吸収し、乾燥してくると空中に水分を放出してくれるのです。目に見える結露はもちろん、床下や壁内などの結露も炭のパワーでしっかりと抑え、カビを発生させずアレルギーにも効果的なのです。
昔、各農家で豚や牛など数頭の家畜を飼っていたころは家庭から出る消し炭を餌に混ぜて与え、整腸に役立てていたようです。最近行われた実験では整腸採用のほかに豚に炭を与えることによって脂肪をコントロールできることがわかっています。赤身の多い豚に育てたい場合や脂肪が付きすぎるといけない養殖豚の場合などに有効だということです。
炭は多孔構造で純粋な炭素に近くミネラルを含みアルカリ性です。長野県の高原野菜栽培農家では、こうした特徴を活かし炭で堆肥をつくり白菜を育てています。病気がなくなり葉が厚くて巻きがしっかりし、甘みのある非常に品質の良いものが収穫しているそうです。ほかにいちご、ほうれんそう、水稲などさまざまな作物に炭が使われはじめています。
奥多摩の汚染していた川をどうにかしたいと主婦のグループが立ち上がりました。生活排水が川に流れ出すところにネット袋に入れた炭をおいたところ、川の水はきれいになり3年後にはウグイが産卵したりホタルがよみがえったそうです。この試みは全国に知られこの河川浄化法をとり入れるところが北海道から九州まで広がっています。
炭を使ったさまざまな食品がありますが、それは今に始まったことではなく昔から炭は食べられていたようです。しかも粉の炭をご飯にかけていたというから驚きです。炭のパワーを腸のお掃除に利用していたとか・・・不純物をスムーズに排泄してくれるようです。おなかの調子が悪いときは炭がいいのかもしれません。
春になると花粉予報が出るほど花粉症に悩まされている人が増えています。しかし、山村のお年寄りたちは「炭焼きが盛んだったころは花粉症などなかった」と言っているそうです。
1972年に中国で発見された2100年前の「馬王堆(マオウタイ)古墳」。棺を開けると出てきたのはまるで数日前に死んだような女性の遺体でした。内臓もしっかりしていて胃の中にあったウリの種を土にまいたら発芽したとか・・・なぜミイラにもならず保存することができたのか波紋を呼びました。棺の周囲には5トンもの炭が埋めつくされており炭の防腐剤効果ではないかと言われています。